
う~ん...フムフム..なるほど...あれっ?...ほほう...それでそれで!
ええっと...やっぱわかんないや...。
って、ひとりで何やってるの?
うわっ、センパイ⁉ いらしてたんですか...アハハ..。(;^_^A
じつは今度の昇格試験の勉強しているのですけど、ちょっと今までサボってたもので...。そうだ、センパイ、勉強の仕方教えてください!
そうだったのね。でも、勉強の仕方というより勉強前の準備に
問題があるように見えるけど。
こんにちはネコ部長です。
試験勉強は何も学生の時だけでの話しではありません。社会に出ても何かしらのテストや試験はあるものです。しかし、仕事をしながら当てずっぽうに勉強しても、なかなか頭には入ってこないし、いい結果も出せませんよね。
じつは結果を出すポイントは、勉強前準備にあったのです。
そこで、結果を出すための実践的な勉強前テクニックがあるので紹介します。
今回の参考著書はこちらです。
勉強前準備テクニック!

世の中には効率的な勉強法というのはたくさん存在しますが、いくら素晴らしい勉強法であっても、その成果を高めてくれる条件が揃っていないと得られる成果には大きな違いが出てきます。その条件を満たしてくれるのが、7つの勉強前準備テクニックです。
① 自己超越目標を持つ ② 知っていることを書き出す ③ 好奇心を刺激する
④ 音楽を正しく使う ⑤ 戦略的リソース利用法 ⑥ 自然の力で集中力を倍にする
⑦ ピアプレッシャーでやる気を出す
それでは順を追って説明していきましょう。
1.自己超越目標を持つ!
最初の準備テク(テクニック)は「自己超越目標」を持つことです。
自己超越目標とは、自分の身の丈を超えた大きな目的やゴールのことで、
自我を忘れて、ただひたすらに目的のために没頭することです。
マズローの「欲求5段階説」のさらに上にある6番目の欲求だそうよ!
どういうことかというと、「良い仕事につきたい」「お金を稼ぎたい」などは、あくまでも自分の欲求を満たすための小さな目標であって、「恵まれない子供たちを助ける仕事につきたい」や「社内試験に合格して社内のシステムを変えていき給与をあげたい」などが自己超越目標になります。
ここで大切なのは、勉強をすることに意味を持たせることです。「恵まれない子供を助けるためにはどのような知識が必要なのか」、「会社や他の社員の役に立ちたい」など、勉強をする目的が明確になることで、モチベーションの質が変わっていくのです。
・世の中をもっと良くする方法がないのだろうか?
・この勉強がそのためにどう役に立つのだろうか?
・自分にとって、最も大事なものとは何だろうか?
このように「自分を超えた大きな価値」について考えることです。
勉強前の10分ほど実践してみてください。
2.知っていることを書き出す!
知らないことを勉強しようとしても、なかなか頭に入ってこないという経験は誰にでもあると思いますが、これは当り前のことで、知らない事ばかりだと最初は楽しくても、だんだん嫌になってきます。
そんな時にやってほしいのが「知っていることを事前に書き出しておく」ことです。
ポイントは次の2つです。
1. 勉強の内容に関りがありそうで、自分がすでに知っている知識は何かと考える
2. 思いついた内容をすべて書き出す
もともと人間の記憶には、古い情報に新しい知識を結びつけながら覚える仕組みができているといわれています。すでに持っている情報が「木の幹」だとすれば、そこから枝葉を遠くまで伸ばしていくのが「学習」なのです。
みなさんは「論語と算盤」という本はご存知でしょうか。
私が 会社で(社長に)この本を薦められたのですが、いざ読もうとしたものの、何のことが書いてあるのかさっぱり分かりませんでした。そこで「論語」や著者の「渋沢栄一」について知っていることを書き出し、それを結び付けながらもう一度本を読んでみると、スルッと頭に内容が入ってきました。
このように少し遠回りのような感じもしますが、頭の準備体操だと思ってください。
3.好奇心を刺激する!
3つ目は、記憶力が簡単にアップするテクニックですが、それは「好奇心を刺激する」ことなのですね。どいうことかというと、人は何か興味があるものに触れると、好奇心を掻き立てられ、脳の中の「報酬系」と呼ばれるエリアが活性化するようです。
このエリアが活性化されるとやる気がアップし、加えて報酬系の隣にある「海馬」と呼ばれる記憶力に大きな影響を与えているところも活発になるというわけです。
よく考えてみてください。あなたは興味のないことを覚えられますか?
人間は好奇心がそそられないものを覚えるのが苦手な生き物なのです。
しかし、勉強で興味がないことまで覚えるにはどうしたら良いのでしょうか?
ここで勉強前準備テク発動です!
・勉強前に好奇心を刺激するようなものに触れておく!
・好奇心が長続きするようなものを選ぶこと!
好奇心をそそられるものは何でもよいそうです。漫画でもアニメでもゲームでも良いそうですが、できれば「謎」の要素が入ったもののほうがよいですね。漫画やアニメでは続きが気になるような作品や、ゲームだとパズル系のほうが好奇心が持続しやすくなるようです。
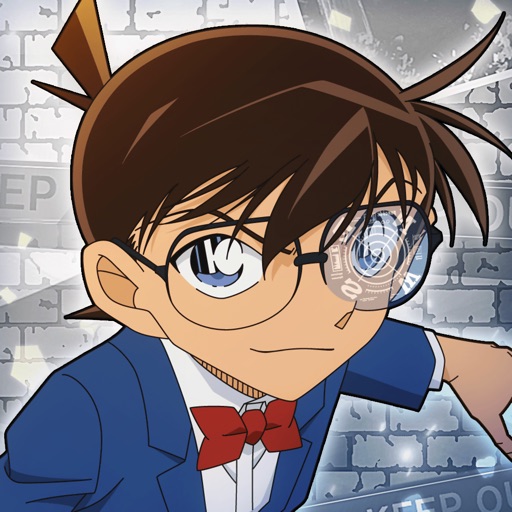
私の体験ですが、以前に仕事で調理の技術や知識を競う大会があったのですが、毎年その大会にチャレンジしていました。しかし、筆記テストがいつも悪くなかなかうまくいかなかったことがありました。ある年のこと、脳トレのゲームが流行っていたことがあり、勉強前にいつもそのゲームをやっていました。すると、今まで苦戦していた筆記テストであっさりと高得点が取れ、その年の大会に見事入賞することができたのでした。
このように、好奇心を誘う工夫が脳の機能をアップさせるということなのです。
4.音楽を正しく使う!
みなさんは勉強中に音楽を聴いていますか?
「好きな音楽を聴かないと勉強がはかどらないですよ」なんていう人もいることでしょう。しかし、残念なことにこれは大きな間違いなのです!勉強中のBGMは効率を上げるどころか、勉強のジャマにしかならないというのです。
グラスゴー大学の実験で、被験者を4種類の部屋に入るように指示しました。
1. テンポの速いBGMの部屋 2. ゆったりとしたテンポのBGMの部屋
3. 環境音(話し声や車のエンジン音) 4. 完全な無音状態
さてこの中で、どの部屋に入った人が一番成績が良かったのでしょうか?
正解は、4番の「完全な無音状態の部屋」の人です。
理由は単純です。BGMは脳への負担が大きすぎるからなのです。
この現象は「無関連音効果」と呼ばれていて、目の前の作業とは関連のない音が耳に入ると、脳はそちらの方へ引き寄せられメロディーやリズムを理解しようとするようです。つまり、脳が2つの情報を同時に処理しようとすることで、脳への負担が増えすぎたため学習能力が下がってしまうということなのです。
ええっ、ダメなんですか?
なにか音楽があった方が気分も上がってきますよ!
どうしても音楽があったほうがいいというかたは、次の方法で実践してください。
1. 勉強の10分前までに好きな音楽を聴く
2. 音楽を止めて勉強をする
3. 勉強の休憩中に、また好きな音楽を聴く
この、2と3を繰り返して学習を進めるのがポイントです。
ただし例外があります。それは「自然音」です。
自然音だけは脳の注意力を上げるようで、小鳥のさえずりや風の音、小川の流れる音などの自然音の効果には、人間にとって程よい集中力を保つのに役立つようです。

5.戦略的リソース利用法!
もともと能力が低いわけではないのに、テストに限って結果が悪かったり、教科書の内容はすぐに理解できているにもかかわらず、なぜか成績に結びついていないという人がいますが、こういったタイプの人は勉強の準備段階でミスをしているかもしれません。
「戦略的リソース利用法」とは、そんなタイプの人に向けてスタンフォード大学が開発したテクニックなのです。そもそも「戦略的リソース」とは、何なのでしょうか?
リソースとは資産や資源のことを指し、戦略的リソースとは問題解決に役立ちそうな
手段やデータ、人材などすべてのことをいいます。
たとえば、学生と社会人とではリソースはこのような感じになります。
学生・・・教科書、参考書、学習サイト、教師、勉強のできる友人
社会人・・・資料、データ、上司、人脈、ビジネス書
このように、どのリソースを利用するかをよく考え、前もって細かい取り組み方を決めておくのが「戦略的リソース利用法」なのです。やり方は7つのステップで行います。
① 成績判断・・どれだけの成績が欲しいかを紙に書き出す
② 重要度測定・・その成績が自分にとってどれだけ重要かを100点満点で採点する
③ 自信測定・・その成績を取るのにどのくらい自信があるかを100点満点で採点する
④ 問題推測・・テストにどんな問題が出そうか予想して紙に書き出す
⑤ 資料抽出・・資料や参考書から勉強に使えそうな箇所を最大15個まで絞り込んで
紙に書き出す
⑥ 理由判定・・その資料や参考書が「使える」と思った理由を紙に書き出す
⑦ 使用法判定・・その資料や参考書をどのように使うつもりかを紙に書き出す
うえぇっ、こんなにあるんですか⁉
一見、難しそうで手間がかかりそうな印象があると思いますが、1日15分ずつ事前に計画を立てるだけでいいので、これをやっていけば必要な参考書や資料の使い方が上手になり、成績も上がってくるようです。ビジネスに置き換えても有効ですよ!
6.自然の力で集中力を倍にする!
4の「音楽を正しく使う!」で触れていますが、自然には私たちの集中力を最適化させる作用があるのです。家にいてもなかなか集中して勉強できないという経験は、誰でも少なからずありますよね。そんな時は、自然の力を借りて効率をアップさせるのがおすすめです。
・自然音のアプリを使う
・勉強机の上に小さな観葉植物を置く
・木々にかこまれた環境で勉強する
特におすすめなのが、「木々にかこまれた環境」です。
イリノイ大学では300人の児童を対象に、自然が多い公園で週1回授業するというグループと、近代的な設備が揃ったクラスルームで週1回授業するという2グループに分けて実験をしたところ、自然の中で授業したグループの集中力が、そうでないグループに比べ2倍も上がっていたという結果が出たのです。
私も休日は、近くの公園に行って読書を しているのよ!
7.ピアプレッシャーでやる気を出す!
集中力って長続きしないものですよね。特に勉強ともなると脳に対する負荷が高いので、すぐ気が散ってしまいがちです。そこでうまく利用するのが「ピアプレッシャー」です。なかなか聞きなれない言葉ですが、意味は「仲間の監視による心理的圧迫感」です。具体的な事例としたら次のようなことがあげられるでしょう。
・上司が残業しているから帰りづらく、無駄な仕事をしている
・違う意見が多いので、別の提案を出しづらくなる
・いじめっ子がクラスメイトをバカにしているので、一緒になっていじめる
このようにピアプレッシャーとは、あまりよくない現象の時に使われてる言葉ですが、これをポジティブに考えてみましょう。するとこのような考えになります。
・まわりが頑張って勉強しているから、自分もやらなければ!
・誰もゴミを捨てていないので、ポイ捨てはしない!
・トイレがキレイにされているから、自分もキレイに使おう!
といった「良いピアプレッシャー」の効果を狙うのです。
これを続けることで、セルフコントロール能力が倍になるといわれています。
でも、自分の意思が弱ければ、なかなか上手くいきませんよね?
そんな時は、あえてモチベーションの高い環境に身を置くことです。
つまり、真剣に勉強している人たちの中で一緒に勉強すれば、ピアプレッシャー効果が高まり自分も集中して勉強することができるのです。
まとめ

いかがでしょうか。
「勉強前準備テクニック」を少しまとめておきましょう。
1. 自己超越目標を持つ!
2. 知っていることを書き出す!
3. 好奇心を刺激する!
4. 音楽を正しく使う!
5. 戦略的リソース利用法!
6. 自然の力で集中力を倍にする!
7. ピアプレッシャーでやる気を出す!
いきなり7つを実践するのは、少しハードなことかもしれませんが 、まずはできることから始めていくことですね。何もしないよりも何かしたほうがいいに決まっているので、少しづつ実践していき習慣化しましょう。
なるほど、センパイありがとうございました!
ということで、センパイには勉強に付き合ってもらい、
プレッシャーを与えてもらいますね!
いやいや、そういうこと言ってるんじゃないんだけれどね...。
ご覧いただきありがとうございました。

